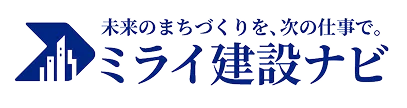「建設業界の経理は特殊だと聞くけれど、具体的に何が違うのだろう?」 「経理としてキャリアアップしたいけれど、どんな資格が評価される?」建設業界で経理の仕事を探している方や、経理部門を強化したい企業の採用担当者なら、一度はこんな疑問を持ったことがあるかもしれません。建設業経リ士は、そんな建設業界特有の会計ルールを熟知した専門家の証です。この記事では、その仕事内容から簿記との違い、資格取得のメリットや具体的な勉強方法まで、網羅的に解説します。
この記事でわかる3つのポイント
・建設業経理士の仕事内容や、一般的な簿記との明確な違い
・資格取得の難易度や合格率、具体的な勉強方法
・採用や転職でどう有利になるのか、企業と個人双方のメリット
建設業経理士とは?建設業界に特化した会計の専門家
建設業経理士とは、その名の通り建設業界に特化した会計知識と処理能力を証明する資格です。一般財団法人建設業振興基金が実施する検定試験で、建設業界における会計のプロフェッショナルとして認められます。
建設業界は、プロジェクトの期間が数ヶ月から数年に及ぶなど、他の産業とは異なる特徴を持っています。そのため、会計処理も特殊なルールに基づいて行われます。この専門的な会計業務を正確に行える人材は、建設会社にとって不可欠な存在です。
一般的な「経理」や「簿記」との違い
「会計の資格なら、日商簿記検定で十分では?」と考える方もいるかもしれません。もちろん、簿記の知識は全ての経理業務の土台となります。しかし、建設業の経理には、簿記の知識だけでは対応しきれない特有の論点が存在します。
最大の違いは、会計処理の対象と目的です。一般的な商業簿記が「商品」を仕入れて販売する企業の会計を扱うのに対し、建設業会計では「工事」を受注し、完成させて引き渡すまでの流れを会計処理します。
| 比較項目 | 一般的な商業簿記 | 建設業会計 |
| 収益の名称 | 売上高 | 完成工事高 |
| 費用の主な科目 | 売上原価、仕入 | 完成工事原価(材料費、労務費、外注費、経費) |
| 特有の勘定科目 | (特になし) | 未成工事支出金(仕掛品に相当)、工事未払金など |
| 作成する書類 | 財務諸表 | 財務諸表+完成工事原価報告書 |
特に重要なのが「未成工事支出金」という勘定科目です。これは、まだ完成していない工事(未成工事)のために支払った材料費や外注費などを一時的に計上しておくためのものです。工事が長期にわたる建設業では、期末時点で未完成の工事が数多く存在するため、この管理が非常に重要になります。
このように、建設業経理士は、日商簿記の知識をベースとしながら、建設業特有のルールを深く理解している専門家なのです。
建設業経理士が企業で重宝される3つの理由
では、なぜ建設業経理士の有資格者は企業から高く評価されるのでしょうか。主な理由は3つあります。
①公共工事の入札で有利になる(経営事項審査での加点)
国や地方自治体が発注する公共工事の入札に参加するには、「経営事項審査(経審)」という審査を受ける必要があります。これは、企業の経営状況や技術力などを客観的に評価する制度です。 この経審の評価点が高いほど、受注できる工事の規模が大きくなります。建設業経理士(1級・2級)の有資格者が社内にいると、この評価点が加算されるため、企業にとって直接的なメリットとなるのです。
②正確な原価計算で会社の利益を守る
建設業は、一つの工事にかかる費用(原価)が非常に大きく、その管理が利益を左右します。材料費、人件費、外注費などを正確に把握し、「この工事は最終的にいくらの利益が出るのか」を予測・管理する「原価計算」は、建設業経理の最も重要な業務の一つです。 建設業経理士は、この複雑な原価計算を正確に行うスキルを持っています。どんぶり勘定を防ぎ、赤字工事のリスクを低減させることで、会社の経営基盤を安定させる重要な役割を担います。
③金融機関や取引先からの信頼度が向上する
建設業特有の会計基準に則った正確な決算書(財務諸表)を作成できることは、会社の信頼性の証明に繋がります。金融機関から融資を受ける際や、新たな取引先と契約する際に、透明性の高い会計情報は非常に重要です。 建設業経理士がいることで、「この会社はしっかりとした会計管理体制が整っている」という評価を得やすくなり、円滑な資金調達や事業拡大に貢献します。
建設業経理士の資格レベルと試験の概要
建設業経理士の資格は、1級から4級までの4つのレベルに分かれています。ここでは、各級の違いと、実務で評価されるレベルについて解説します。
1級〜4級の違いと目指すべきレベル
・4級: 建設業経理の入門レベル。簿記の基本的な仕組みと、建設業で使われる初歩的な勘定科目を学びます。
・3級: 建設業の基本的な原価計算や、日常的な会計処理を担えるレベル。日商簿記3級程度の知識に、建設業の要素が加わります。
・2級: 実践的な原価計算や、決算業務までを行える実務レベル。履歴書に書いてアピールできるのは、一般的にこの2級以上です。経営事項審査での評価対象にもなり、転職やキャリアアップで有利になります。
・1級: 高度な原価計算、財務分析、経営分析まで行えるエキスパートレベル。科目が「財務諸表」「財務分析」「原価計算」の3つに分かれており、科目合格制が採用されています。企業の経理部門の管理職や、経営層への助言も期待される高度な専門人材です。
【2025年度版】試験日程・受験資格・試験内容
試験は、主に以下のスケジュールで実施されます。
・上期試験(9月上旬): 1級(財務諸表・財務分析)、2級、3級、4級
→第38回(上期): 2025年9月7日(日)
・下期試験(3月上旬): 1級(全3科目)、2級、3級、4級
→第39回(下期): 2026年3月1日(日)
※正確な日程は、必ず公式サイトでご確認ください。
- 受験資格: 学歴、年齢、国籍、実務経験などの制限はなく、誰でも受験できます。
- 試験内容:
- 1級: 財務諸表、財務分析、原価計算の3科目(科目ごとに受験)
- 2級: 建設業の実践的な原価計算、会社会計
- 3級: 建設業の基本的な原価計算、簿記
- 4級: 簿記のしくみ
- 受験料(税込): 受験料は改定される可能性があるため、目安としてご覧ください。
- 1級: 1科目 8,220円
- 2級: 7,120円
- 3級: 6,120円
- 4級: 5,120円
気になる合格率と難易度をレベル別に解説
各級の難易度を、最新の合格率データから見てみましょう。2級は合格率30〜40%台で、日商簿記2級と同程度かやや易しいレベルですが、建設業特有の内容に慣れる必要があります。1級は科目別に15〜30%と低く、特に原価計算が難関です。3科目合格には複数回の受験が一般的です。
【第36回(2024年9月実施)試験結果】
| 級 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1級(財務諸表) | 1,228人 | 291人 | 23.7% |
| 1級(財務分析) | 1,023人 | 294人 | 28.7% |
| 1級(原価計算) | 1,323人 | 200人 | 15.1% |
| 2級 | 7,656人 | 2,752人 | 36.0% |
| 3級 | 5,595人 | 3,116人 | 55.7% |
| 4級 | 609人 | 490人 | 80.5% |
建設業経理士の資格取得に向けた勉強方法
ここからは、資格取得を目指す方向けに、具体的な勉強方法を解説します。
独学でも合格は可能?メリット・デメリット
結論から言うと、2級までであれば独学での合格は十分に可能です。
独学のメリット:
費用を抑えられる(テキスト・問題集代のみ)
自分のペースで学習を進められる
独学のデメリット:
モチベーションの維持が難しい
疑問点をすぐに解決できない
法改正などの最新情報を見逃す可能性がある
市販のテキストと過去問題集を繰り返し学習することが基本になります。まずは評価の高いテキストを1冊選び、全体像を掴んだ後、ひたすら過去問を解いて出題形式に慣れるのが王道です。
おすすめの勉強ステップと期間の目安
効率的に学習を進めるためのステップと、必要な勉強期間の目安を紹介します。
- 簿記の基礎を固める: 簿記の知識が全くない方は、まず日商簿記3級レベルの学習から始めましょう。これが理解の土台になります。
- テキストを読み込む: 建設業経理士のテキストで、特有の勘定科目や原価計算の流れを理解します。
- 個別問題を解く: 各論点(材料費の計算、労務費の計算など)の個別問題を解き、知識を定着させます。
- 過去問題を解く: 過去5回分以上の過去問を、時間を計って本番同様に解きます。間違えた箇所は、なぜ間違えたのかを徹底的に復習することが合格への近道です。
【勉強期間の目安(2級)】
- 簿記知識がない方: 200〜300時間(日商簿記3級の学習時間を含む)
- 日商簿記3級程度の知識がある方: 150〜200時間
- 日商簿記2級程度の知識がある方: 80〜120時間
1日に2時間勉強するなら、簿記知識のある方で3〜4ヶ月が目安となります。計画的に学習を進めましょう。
日商簿記とのダブルライセンスを目指す際のコツ
建設業界以外でも通用する会計スキルを身につけたいなら、日商簿記とのダブルライセンスが非常に有効です。
目指す順番としては、「日商簿記を先に取得する」ことを強くおすすめします。 日商簿記2級で学ぶ商業簿記・工業簿記の知識は、建設業会計を理解する上で大きな助けとなります。特に工業簿記の原価計算の考え方は、建設業の原価計算と共通する部分が多く、学習をスムーズに進めることができます。
日商簿記2級 → 建設業経理士2級という順番で取得すれば、会計の基礎力と建設業への専門性を兼ね備えた、市場価値の高い人材になることができるでしょう。
資格を活かす!建設業経理士のキャリアと将来性
最後に、資格をどのように仕事に活かせるのか、具体的なキャリアパスと将来性について見ていきましょう。
採用で有利!主な就職先と仕事内容
建設業経理士の資格は、建設業界のあらゆる企業で求められます。
・ゼネコン(総合建設業者)
・サブコン(専門工事業者)
・ハウスメーカー
・工務店
・プラント・エンジニアリング会社
・建設コンサルタント会社
・日々の伝票処理、入出金管理
・工事ごとの原価計算、予算管理
・月次・年次決算業務
・完成工事原価報告書の作成
・経営事項審査に関する書類作成
・資金繰り、銀行との折衝
建設業界は安定した需要があり、今後もインフラの維持・更新などで仕事がなくなることは考えにくい業界です。専門知識を持つ経理人材は常に需要があるため、安定したキャリアを築きやすいと言えます。
経営事項審査での加点で企業に大きく貢献
前述の通り、1級・2級の資格は経営事項審査(経審)の評点に直接繋がります。これは、求職者にとっても企業にとっても最大のメリットと言えるでしょう。
経審の評価項目のうち、「W点(その他社会性等)」の中に「公認会計士等数」という項目があり、有資格者の数に応じて点数が加算されます。
- 1級建設業経理士: 1人につき 1点 加算
- 2級建設業経理士: 1人につき 0.4点 加算
このわずかな点数が、受注できる公共工事のランクを左右することもあります。有資格者を採用することは、企業の売上や事業規模の拡大に直結する重要な経営戦略なのです。
実は、建設業経理士の1級・2級は、公共工事の入札に参加する企業が受ける経営事項審査(経審)で評価されるために、5年ごとの更新(有料の講習受講)が必要です。
単に資格を持っているだけでなく、最新の知識を学び続けている証明にもなります。採用担当者の方は、応募者の資格取得年や更新状況も確認すると良いでしょう。
資格手当やキャリアアップの可能性は?
多くの建設会社では、建設業経理士の資格に対して資格手当を支給しています。 相場としては、2級で月額3,000円〜10,000円、1級で月額10,000円〜30,000円程度が一般的です。これは、社員のスキルアップを奨励すると同時に、経審での評価点を維持したいという企業側の意図もあります。
また、資格取得は明確なスキル証明となるため、昇進・昇格の際にも有利に働きます。経理担当者から経理主任、課長、そして将来的には会社の財務全体を管理するCFO(最高財務責任者)への道も開ける可能性を秘めています。
まとめ:建設業経理士は採用とキャリアの双方に価値ある資格
この記事では、建設業経理士の概要から取得のメリット、勉強方法までを網羅的に解説しました。
【この記事のまとめ】
- 建設業経理士は、建設業界に特化した会計の専門家であり、一般的な簿記とは異なる知識が求められる。
- 特に2級以上は、経営事項審査での加点に繋がり、企業の受注機会拡大に直接貢献するため価値が高い。
- 資格取得は転職やキャリアアップに有利に働き、資格手当などの金銭的なメリットも期待できる。
- 取得を目指すなら、まず日商簿記の基礎を固めてから、建設業経理士2級に挑戦するのが効率的。
建設業経理士は、求職者にとっては「専門性を武器に、安定した業界で活躍できる」キャリアを築くための強力なパスポートです。 そして、採用担当者や経営者にとっては「会社の信頼性を高め、事業を成長させる」ための重要なキーパーソンとなり得ます。
多様な人材が活躍するこれからの建設業界において、その根幹を支える会計のプロフェッショナルの重要性は、ますます高まっていくことは間違いありません。