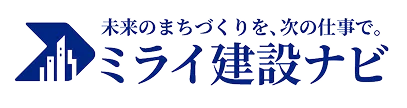建設業界で事業を行う上で、避けては通れないのが「建設業法」です。この法律は、建設工事の品質確保や発注者の保護、そして業界の健全な発展のために存在します。
「法律は難しくてよくわからない…」と感じる方も多いかもしれません。しかし、知らずに違反してしまうと、営業停止や許可取り消しといった重い罰則が科されるリスクも。
この記事では、建設業法の基本から最新の改正情報まで、初めての方にも分かりやすく解説します。コンプライアンスを遵守し、信頼される企業として成長していくため、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を読むことで得られる3つのポイント
・建設業を営む上で根幹となる「建設業法」の目的と全体像
・「許可制度」「契約ルール」「技術者設置」など、遵守すべき主要なルール
・法律に違反した場合の具体的な罰則やリスク、最新の法改正の動向
建設業法とは?事業の根幹となる法律の基本
まず、「建設業法」がどのような法律で、なぜ必要なのか、そしてどのような工事が対象となるのか、という基本的な部分から見ていきましょう。この法律の全体像を掴むことが、理解への第一歩です。
なぜ建設業法は必要なのか?その目的を解説
建設業法は、一言でいえば「建設業界の健全な運営と発展のためのルールブック」です。
法律の条文(第1条)には、その目的が次のように書かれています。
建設業法 第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
少し難しい言葉が並んでいますが、分解すると大きく2つの目的が見えてきます。
建設工事は、私たちの生活の基盤となる住宅、道路、橋、学校などをつくる、社会にとって非常に重要な仕事です。もし、技術力のない業者が施工したり、不誠実な契約で手抜き工事が行われたりすれば、建物の安全性が脅かされ、最悪の場合、人命に関わる大事故に繋がる恐れがあります。また、工事の発注者(工事を依頼するお客様)は、建設に関する専門知識を持っていないことがほとんどです。そのため、業者との間に知識や情報の差が生まれやすく、不利な契約を結ばされたり、欠陥のある工事をされたりするリスクがあります。こうした事態を防ぎ、「工事の品質をしっかり確保すること」そして「専門知識のない発注者を守ること」が、建設業法の最も重要な目的の一つです。
もう一つの目的は、「建設業界全体が健全に成長していくこと」です。 悪質な業者が自由に参入できてしまうと、真面目に技術を磨いている優良な業者が正当に評価されず、業界全体の信頼性が低下してしまいます。そこで建設業法は、一定の技術力や経営能力を持つ業者だけが事業を行えるように「許可制度」を設けたり、業者間の不公平な取引を禁止したりすることで、公正な競争環境を整えています。これにより、業界全体の技術力や経営基盤が向上し、持続的に発展していくことを目指しているのです。
建設業法は、単に業者を縛るための法律ではありません。「発注者を守り、優良な業者が正当に評価される環境をつくることで、社会インフラの安全と建設業界の未来を守る」ための、非常に重要な法律なのです。
対象となる「建設工事」とは?具体例で確認
建設業法は、すべての「ものづくり」に適用されるわけではありません。「建設工事」に該当する仕事が対象となります。では、具体的にどのような工事が「建設工事」なのでしょうか。
法律では、建設工事を以下の2種類の一式工事と27種類の専門工事、合計29業種に分類しています。
■一式工事(2業種) 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物や土木工作物を建設する工事です。複数の専門工事を組み合わせて行う大規模な工事がこれにあたります。
・土木一式工事:道路、橋、ダム、トンネル、河川工事など
・建築一式工事:住宅、ビル、学校、病院などの新築、増改築など
■専門工事(27業種) 一式工事以外の、それぞれの専門分野に特化した工事です。
- 大工工事:木材の加工や取付けにより工作物を築造する工事
- 左官工事:壁塗り、床塗りなど、塗り作業全般
- とび・土工・コンクリート工事:足場の組立て、基礎工事、コンクリート打設など
- 石工事:石材の加工又は積方により工作物を築造する工事
- 屋根工事:瓦、スレート、金属薄板等による屋根ふき工事
- 電気工事:発電設備、送配電線、照明設備などの設置工事
- 管工事:冷暖房、空調、給排水、ガス管などの設備工事
- タイル・れんが・ブロック工事:タイルやブロックなどを張付け・築造する工事
- 鋼構造物工事:鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事など
- 鉄筋工事:鉄筋の加工・組立工事
- 舗装工事:道路等のアスファルト舗装、コンクリート舗装工事
- しゅんせつ工事:河川、港湾等の水底の土砂などを掘削する工事
- 板金工事:金属薄板等を加工して工作物に取付ける工事
- ガラス工事:工作物にガラスを加工して取付ける工事
- 塗装工事:塗料などを工作物に吹付け、塗付けする工事
- 防水工事:アスファルト、モルタル、シーリング材等による防水工事
- 内装仕上工事:インテリア工事、天井仕上工事、床仕上工事、間仕切り工事など
- 機械器具設置工事:プラント設備、エレベーター、立体駐車場設備などの設置工事
- 熱絶縁工事:冷暖房設備、冷凍冷蔵設備などの熱絶縁工事
- 電気通信工事:有線・無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの工事
- 造園工事:植栽工事、地盤改良、景石工事、公園設備工事など
- さく井工事:ボーリングマシンなどによる、さく井(井戸掘り)、温泉掘削工事
- 建具工事:窓枠やドアなどの金属製・木製建具の取付け工事
- 水道施設工事:上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設工事
- 消防施設工事:屋内・屋外消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、火災報知設備工事など
- 清掃施設工事:ごみ処理施設、し尿処理施設などの工事
- 解体工事:工作物の解体を行う工事
自社が行う工事が、この29業種のどれに該当するのかを正確に把握することが非常に重要です。
■建設業許可が不要な「軽微な建設工事」 上記の工事に該当する場合でも、すべてのケースで許可が必要なわけではありません。国民生活に与える影響が比較的小さい「軽微な建設工事」については、建設業許可がなくても請け負うことが可能です。
「軽微な建設工事」と判断される基準は以下の通りです。
| 工事の種類 | 金額(消費税込み) |
| 建築一式工事 | 1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外 | 500万円未満の工事 |
例えば、内装仕上工事(専門工事)を400万円で請け負う場合は許可は不要ですが、600万円で請け負う場合は許可が必要になります。この金額を超えて無許可で工事を請け負うと、厳しい罰則の対象となります。
必ず押さえるべき建設業法の3大ルール
建設業法には多くの規定がありますが、事業を行う上で絶対に理解しておくべき、特に重要なルールが3つあります。それが「建設業許可」「請負契約のルール」「技術者の設置」です。これらは法律の根幹をなすものであり、違反は企業の存続を揺るがしかねません。
ルール1|事業のスタートライン「建設業許可」
前述の「軽微な建設工事」を超える規模の工事を請け負うためには、必ず「建設業許可」を取得しなければなりません。これは、いわば国や都道府県から「建設業者として事業を行うに足る能力がある」とお墨付きをもらうためのライセンスです。
許可を得るためには、主に5つの要件をクリアし、それを証明する書類を提出する必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること 法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人が、建設業の経営について一定の経験を持っている必要があります。具体的には、許可を受けたい業種で5年以上、またはそれ以外の業種で6年以上の経営経験などが求められます。これは、ずさんな経営による倒産などを防ぎ、安定した事業運営を担保するための要件です。
- 専任技術者を営業所ごとに置いていること 許可を受けたい業種に関して、一定の国家資格(例:1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士など)を持っているか、または10年以上の実務経験を持つ技術者を、各営業所に常勤で配置しなければなりません。これは、工事の品質を技術的な側面から保証するための要件です。
- 誠実性があること 法人の役員や事業主などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。過去に法律違反で処分を受けたり、暴力団員であったりすると、この要件を満たせない場合があります。
- 財産的基礎または金銭的信用があること 工事を途中で投げ出すことなく、最後まで完成させるための資金力があるかどうかが問われます。具体的には、自己資本の額が500万円以上あることや、500万円以上の資金調達能力があることなどを証明する必要があります。
- 欠格要件に該当しないこと 許可申請書に虚偽の記載があったり、役員などが成年被後見人や破産者であったり、過去に建設業許可を取り消されてから5年が経過していなかったりするなど、法律で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。
これらの要件は、建設業者としての「経営」「技術」「資金」「信頼性」を総合的に審査するためのものであり、一つでも欠けていると許可は下りません。
「一般」と「特定」の違いとは?
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つの区分があります。この違いは、自社が元請(発注者から直接工事を請け負う立場)になった際に、下請業者に出す工事の金額規模によって決まります。
| 許可の種類 | 下請に出す工事の合計金額 (1つの工事あたり) | 特徴 |
| 一般建設業許可 | 4,500万円未満 (建築一式工事の場合は7,000万円未満) | 多くの建設業者がまず取得する基本的な許可。 |
| 特定建設業許可 | 4,500万円以上 (建築一式工事の場合は7,000万円以上) | 大規模な工事を元請として受注し、多くの下請業者を管理する場合に必要。下請業者を保護する責任が重くなるため、財産的要件や技術者要件が「一般」よりも格段に厳しくなる。 |
【具体例】
ある建設会社が、発注者Aから1億円のビル建設工事(建築一式工事)を元請として受注した場合。
・ケース1: 自社でほとんどの工事を行い、下請の内装業者Bに6,000万円の工事を発注する場合 → 下請契約額が7,000万円未満なので、「一般建設業許可」でOK。
・ケース2: 自社は全体の管理を行い、下請の鉄骨工事業者Cに8,000万円の工事を発注する場合 → 下請契約額が7,000万円以上になるため、「特定建設業許可」が必要。
特定建設業許可が必要なのは、大規模工事において元請が多くの下請業者を束ねる元締めのような役割を担うためです。元請に万が一のことがあっても下請業者が連鎖倒産するような事態を防ぎ、工事全体を円滑に進めるために、より重い責任と能力が求められるのです。
ルール2|トラブルを防ぐ「請負契約」の決まり
建設工事は、完成までに長期間を要し、金額も高額になることが多いため、契約に関するトラブルが発生しやすいという特徴があります。そこで建設業法は、契約内容を明確にし、当事者間のトラブルを未然に防ぐための詳細なルールを定めています。
■書面による契約の締結(建設業法第19条) 最も基本となるのが、契約内容を必ず書面(契約書)で残すことです。「言った・言わない」の争いを防ぐため、口約束での契約は認められていません。契約書には、法律で定められた以下の事項を記載し、当事者双方が署名または記名押印して、お互いに保管することが義務付けられています。
・工事内容
・請負代金の額
・工事着手および完成の時期
・請負代金の支払いの時期および方法
・設計変更や工期変更があった場合の取り決め
・天災など不可抗力による損害の負担について
・契約不適合(以前の「瑕疵担保」)に関する保証
・紛争解決の方法
・(その他、法律で定められた事項)
■見積りのルール(建設業法第20条) 契約前には、発注者に対して工事費用の内訳をできる限り明らかにした見積書を提示する努力義務があります。これにより、発注者は工事内容と費用の妥当性を判断しやすくなります。
■一括下請負(丸投げ)の禁止(建設業法第22条) 元請業者が、受注した工事をそのまま、あるいは実質的にすべてを下請業者に任せてしまう「一括下請負(丸投げ)」は、原則として固く禁止されています。
■元請負人の義務 元請負人には、下請負人を守るためのさまざまな義務が課されています。
- 不当に低い請負代金の禁止:元請の都合で、通常必要な費用を大幅に下回る金額で下請契約を強要してはいけません。
- 不当なやり直し等の禁止:下請負人に責任がないにもかかわらず、やり直しをさせたり、費用を負担させたりしてはいけません。
- 代金の早期支払い:下請負人から工事完成の通知を受けたら、速やかに検査を行い、定められた期日までに代金を支払わなければなりません。
これらの契約ルールは、立場の弱い下請業者を保護し、公正な取引関係を築くことで、建設業界全体の健全性を保つために不可欠なものです。
ルール3|工事品質を担う「技術者」の設置義務
建設工事の安全と品質を確保するため、工事現場には必ず専門の技術者を配置することが法律で義務付けられています。この技術者は、工事が設計図書通りに、かつ安全に行われるよう、現場全体を技術的に管理・監督する「現場の指揮官」のような存在です。
技術者には大きく分けて「主任技術者」と「監理技術者」の2種類があります。
■主任技術者
- 配置義務:すべての建設工事現場に配置が義務付けられています。元請・下請に関わらず、また工事金額の大小に関わらず、自社が施工する工事現場には必ず主任技術者を置かなければなりません。
- 役割:施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理など、工事施工に関する技術上の管理全般を行います。
■監理技術者
- 配置義務:「特定建設業許可」を持つ業者が、発注者から直接請け負った工事(元請工事)で、下請契約の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)になる場合に、主任技術者に代わって配置が義務付けられます。
- 役割:主任技術者の業務に加えて、下請業者(主任技術者)への適切な指導・監督という、より広範で重い責任を担います。いわば「現場監督の、さらにその上の監督」です。
■主任技術者と監理技術者の違い(まとめ)
| 主任技術者 | 監理技術者 | |
| 役割 | 現場の技術的な管理 | 現場の技術的な管理+下請業者への指導監督 |
| 配置が必要な現場 | すべての工事現場 | 特定建設業者が元請として施工する大規模な工事 |
| 必要な資格・経験 | ・1級または2級の国家資格者 ・学歴に応じた実務経験者 など | ・1級の国家資格者 ・指導監督的実務経験者 など |
「専任」とは、その工事現場に常時継続して勤務することを意味し、原則として他の工事現場との兼任は認められません。これは、重要な工事に集中して技術的管理を行わせることで、工事の品質と安全をより確実にするための措置です。
企業の採用担当者や経営者は、受注した工事の規模に応じて、必要な資格を持つ技術者を適切に配置できる体制を整えておく必要があります。また、転職を考える技術者にとっては、自身の資格や経験がどのレベルの技術者に該当するのかを理解しておくことがキャリアアップに繋がります。
【2025年施行】建設業法改正の重要ポイント
建設業界は、働き手の高齢化や若者の入職者減少といった深刻な課題に直面しています。この状況を打破し、持続可能な産業へと転換するため、建設業法も時代に合わせて改正が続けられています。 現在の時刻は2025年7月であり、2025年4月に施行された改正は、特に「働き方」と「担い手確保」に焦点を当てた重要な内容となっています。
働き方改革の推進|時間外労働の上限規制
建設業界では、これまで「36協定」を結べば事実上、時間外労働の上限なく働くことが可能でしたが、猶予期間が終了し、2024年4月から時間外労働の上限規制(原則として月45時間・年360時間)が罰則付きで適用されています。
今回の建設業法改正は、この働き方改革関連法の遵守を後押しする内容となっています。
■著しく短い工期による請負契約の禁止
改正法では、中央建設業審議会が作成する「工期に関する基準」に照らして「著しく短い工期」となる請負契約を結ぶことが、発注者・受注者ともに禁止されました。 これは、無理な工期が長時間労働の温床となっている実態を踏まえたものです。これに違反した場合、国土交通大臣や都道府県知事から勧告や命令を受ける可能性があります。
これにより、元請業者は無理な工期での受注を断る法的根拠を得やすくなり、発注者側も適正な工期設定への理解が求められることになります。
担い手確保へ|処遇改善と生産性向上
魅力ある職場環境をつくり、将来の担い手を確保するための改正も行われました。
■下請代金への労務費相当額の反映 元請業者は、下請業者と契約を結ぶ際、労務費(賃金)の動向や、資材価格の変動を適切に反映した金額を設定するよう努めることが求められます。見積時から労務費を内訳として明示し、賃上げの原資がきちんと下請業者、そして現場で働く技能者まで行き渡るような仕組みづくりが推進されています。
■施工体制台帳の記載事項の追加 元請業者が作成する「施工体制台帳」(工事に関わるすべての下請業者などを記載した書類)に、「社会保険の加入状況」に加えて「技能者の賃金水準」などを記載することが求められるようになりました。これにより、技能者の処遇が適切であるかを可視化し、改善を促す狙いがあります。
■ICT活用による生産性向上 資材の調達や管理、現場の検査などをICT(情報通信技術)を活用して効率化することも法律で後押しされています。例えば、遠隔での臨場(立ち合い検査)やドローンを使った測量などがこれにあたります。生産性を向上させることで、長時間労働を是正し、働きやすい環境をつくることを目指しています。
もし建設業法に違反してしまったら?
建設業法は、業界の健全な発展を守るためのルールブックであると同時に、違反者には厳しいペナルティが科されることを定めています。軽い気持ちでの違反が、会社の信用を失墜させ、事業の継続を困難にさせることもあります。「知らなかった」では済まされません。
違反した場合の罰則は、大きく分けて「行政処分」と「刑事罰」の2種類があります。
行政からの3つの重い処分
監督行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)は、法律違反が確認された建設業者に対して、その内容や悪質性に応じて段階的な行政処分を下します。
①指示処分 行政処分の中で最も軽い処分です。法律違反の状態を是正するために、具体的な措置をとるよう「指示」されます。いわば行政からの「イエローカード」です。
対象となる違反例:
一括下請負(丸投げ)を行った
主任技術者を適切に配置しなかった
契約書を交わさずに工事を行った
施工体制台帳を作成しなかった この指示に従わない場合は、より重い「営業停止処分」に繋がります。
②営業停止処分 指示処分に従わない場合や、違反が悪質・重大である場合に下される重い処分です。期間を定めて、建設業に関する営業活動の全部または一部を停止させられます。期間は1年以内の範囲で定められます。
対象となる違反例:
指示処分に従わない
特定建設業者が、下請代金の支払いを不当に遅延させた
談合や贈賄など、他の法律に違反して罰金刑などを受けたなど
③建設業許可の取消処分 最も重い行政処分です。建設業の許可そのものが取り消され、事業を継続することができなくなります。いわば「レッドカード」であり、業界からの退場を意味します。
対象となる違反例:
営業停止処分に違反して営業を続けた
許可の要件(経営業務の管理責任者、専任技術者など)を欠いた状態が続いた
会社の役員などが、禁錮以上の刑に処せられるなど欠格要件に該当した
不正な手段で許可を取得したことが判明した 一度許可を取り消されると、原則として5年間は新たに許可を取得することができません。
罰則は、法人の代表者や従業員個人だけでなく、法人そのものにも科されることがあります(両罰規定)。刑事罰を受ければ前科がつき、企業の信用失墜は避けられません。
建設業界の未来と法遵守の重要性
ここまで建設業法のルールと罰則について見てきましたが、最後に、これからの建設業界において、法律を遵守することがなぜ一層重要になるのかを考えていきましょう。特に、業界最大の課題である「人材」との関わりは無視できません。
まとめ|建設業法の理解が企業の未来を守る
この記事では、建設業法の目的から3大ルール、法改正、そして違反時の罰則までを網羅的に解説しました。
建設業法は、決して難解で複雑なだけの法律ではありません。その根底には、「工事の安全を守り、発注者を守り、真面目な業者が正当に評価される業界をつくる」という、明確でポジティブな思想が流れています。
変化の激しい時代だからこそ、その土台となる法律を正しく理解し、遵守する姿勢が、企業の持続的な成長と、建設業界全体の明るい未来を築く鍵となるのです。